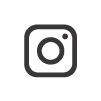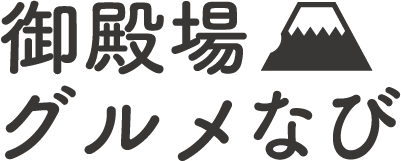インタビュー:鈴木平作さん(御殿場小山水かけ菜生産組合 組合長)
― まず、水かけ菜の歴史や特徴について教えてください。
水かけ菜は、御殿場小山地域の冬の伝統野菜で、明治19年頃から作られているといわれています。もともとは稲刈りが終わった田んぼの裏作として栽培され、冬の貴重な青菜として親しまれてきました。特徴としては、寒さにさらされることで甘みが増し、シャキシャキとした食感が楽しめることです。
また、御殿場は寒冷地なので冬場に露地野菜を作るのが難しく、昔はこの水かけ菜が地域の貴重な野菜だったんです。御殿場で駐屯した自衛隊の方々が全国に転勤する際に御殿場の味として広まり、全国各地から注文が来るようになりました。

― 水かけ菜生産組合はどのような経緯で設立されたのでしょうか?
もともとは各農家が個別に水かけ菜を市場へ出荷していましたが、流通量が多くなると価格が下がり、持続的な生産が難しくなりました。そこで、約40年前に組合を作り、漬物として販売することで価値を高める取り組みを始めました。最盛期には組合だけで年間60トンもの水かけ菜を生産していたんです。
― 現在の生産状況はどうでしょうか?
現在は組合員が約27名と減少し、個人で生産している方も含めても100人に満たない程度になっています。特に最近では、農家の高齢化や漬物製造の営業許可制度の影響で生産者が減り、今年の出荷量は10トン程度にまで落ち込んでいます。かつての60トンと比べると、かなり厳しい状況ですね。
さらに、今年は冬場の異常気象が影響しました。11月から1月にかけてほとんど雨が降らず、寒さが厳しかったため生育が遅れました。こうした天候の影響は避けられず、生産の安定化が大きな課題です。

― 水かけ菜の魅力はどのような点でしょうか?
一番の魅力は、寒さに耐えた後に増す甘みと、独特のシャキシャキした食感ですね。特に、2~3cmの雪が積もった後に収穫すると、野菜自身が凍らないように糖分を蓄えるため、味がぐっと良くなるんです。
また、漬物がメインですが、実はさまざまな料理に活用できます。おひたしや卵とじ、鍋の具材としてもおすすめですし、細かく刻んでチャーハンやパスタに加えても美味しいですよ。最近では、消費者の方がいろんなアレンジをして楽しんでくださっています。

― 3月22日の「ごてんば酒と食のフェスティバル」では、水かけ菜はどのように提供されるのでしょうか?
イベントでは、水かけ菜の漬物を中心に販売します。また、数量は限られますが、水かけ菜を使用した特製丼も提供予定です。丼は限定800食となっており、イベントの目玉の一つとしてPRできればと思っています。
― 来場者へのメッセージをお願いします。
水かけ菜は、御殿場小山ならではの伝統野菜です。生産量が減少しつつある中で、少しでも多くの方に味わっていただき、魅力を知っていただければ嬉しいです。御殿場の冬を感じる味として、ぜひこの機会に楽しんでください!